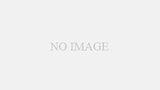こんにちは、元声優志望で現在は外資系コンサルタントとして働いているKotonoです。
2025年2月に公開された「赤いきつねと緑のたぬき」の新作アニメCMが突然の炎上騒動に巻き込まれ、SNS上で賛否両論が繰り広げられています。
人気カップ麺ブランドがなぜ思わぬ批判を浴びることになったのかは、私個人としてとても興味深いトピックスだなと思っています。
炎上の表向きのトリガーは、泣き顔で麺をすする女性キャラが「性的表現なのでは?」という指摘を受けたこと。
その背後にはアニメ文化に根付いた男性目線(Male Gaze)や、日本社会で長らく続いてきた女性の性客体化の問題が潜んでいるように見えます。
企業のマーケティング戦略の観点から、
- なぜこんな炎上が起きたのか?
- 無意識に働くジェンダーバイアスが与える影響は?
- アニメ表現と実社会の“ズレ”
を多角的に考察してみたいと思います。
1. CM炎上のあらまし:何が批判を引き起こしたのか
1-1. 「泣き顔の女性キャラ」を巡る物議
このCMでは、女性キャラクターが夜の部屋でドラマを観て感動し、涙ぐみながらカップ麺をすする姿が描かれています。
頬が赤らみ、瞳が潤んだ状態で麺をすすっている演出に対し、SNS上では「これは男性目線で女性をセクシーに描いている」「なんとなくフェチっぽさを感じる」などの批判が噴出。
一方、「泣いているんだから目が潤んで頬が赤いのは当然」という擁護意見が多数見られました。
しかし、そもそもカップ麺の宣伝に“泣き顔で頬を赤らめている女性”が必須か? という疑問を私個人としては感じずにはいられません。
むしろ、涙目で潤んだ瞳や泣いた後の赤らんだ頬を見せたいがために、「泣けるドラマをみている」という要素を追加したようにも見えてしまいます。
1-2. 男性版CMとの比較と「不公平感」
同時期に公開された男性版のCMは、夜の職場で男性が淡々とカップ麺を食べるという演出。こちらには涙や頬染めの要素はなく、より実務的でシンプルな映像でした。
「女性にはわざわざ泣かせて、男には平然と仕事をさせるなんてアンバランスだ」との声もあり、女性キャラだけ色っぽく(あるいは感情的に)描くのは、ジェンダーバイアスでは? と炎上が加速しました。
1-3. 制作側の意図:単なる“温かさ”の表現?
広告主や制作者サイドは「あくまで深夜にリラックスして感動しながら食べる瞬間を描きたかっただけ」と説明しているようですが、SNSでは「それがなぜ男性には適用されず、女性だけがドラマを見て涙を流してるの?」と根本の意図に疑念を持たれています。
炎上マーケティングを狙ったとも思えず、企業側としてはむしろ困惑しているかもしれません。
しかし、ここには“無意識のジェンダーバイアス(アンコンシャス・バイアス)”が見え隠れしているのではないでしょうか?
2. 男性目線(Male Gaze)と日本のアニメ文化が生む表現の歪み
2-1. アニメ表現×性客体化:声優を志す視点で考える
アニメ文化では、泣き顔や頬染め、涙目といった演出がキャラクターの“かわいさ”や“魅力”を強調する定番手法です。
声優志望の方なら、「あざとい仕草」「甘える声質」「涙混じりの演技」などが定番の“萌え要素”として好まれることをご存じかもしれません。
これが極端になると、女性キャラは常に男性視聴者の欲望を満たすオブジェクトとして描かれてしまう(Male Gaze)。
無意識のうちに“女性=可愛く泣いている、庇護すべき存在(男性と比較した時の弱者)”という図式をメディアが再生産してしまうわけです。
2-2. 男性視点が古くから根づいた理由
「女性を性的なものとして描くのが当たり前」という感覚は、日本のアニメ文化や広告制作の現場で長年“標準”とされてきた部分があるのかもしれません。
- 女性キャラを可愛い・弱々しい存在として描くほど男性視聴者の支持を得られる
- セクシーさを全面に出すと注目が集まる
- 制作スタッフ自体がほぼ男性で構成されている
こうした背景から、女性キャラに“泣き顔+頬染め”を持たせる演出が無意識に採用されているケースも多いのではないでしょうか。
このCMを擁護する人たちからは「今回の制作者は女性である」と意見がありますが、あまり関係はないと私個人としては思います。
アニメの制作の上位層や広告の現場は依然として男性が多い職場です。
男性社会で暮らしてきた女性は無意識に男性に迎合する、なんてことは古くから、フェミニズム研究でも言われてきています。
- ストラテジック・マスキュリニティ
女性が成功のために、男性的な言動や態度を意図的に採用すること。例えば、リーダーシップを発揮する際に、社会的に期待される「優しさ」や「協調性」ではなく、「攻撃性」や「決断力」を強調する。 - クイーンビー症候群
性が男性優位の環境で成功するために、他の女性と距離を置いたり、女性らしさを抑えたりする現象。上位にいる女性が、他の女性の昇進を妨げることも含まれる。1970年代に研究され始め、職場環境で特に指摘される。 - インポスター症候群(Imposter Syndrome)と関連
女性が「女性らしさ」を保ったまま成功することが難しい環境では、自己の能力に疑念を抱き、「男性のように振る舞わなければならない」と感じることがある。
3. マーケティングの視点:企業が失ったバランスと炎上リスク
3-1. なぜ企業は炎上を予測できなかったのか?
- ターゲット設定の甘さ
- 「夜にほっと温まる」というテーマを女性キャラに落とし込むのは自然かもしれませんが、その演出方法がやや“偏った視点”に陥っていなかったか。
- 多角的チェック不足
- ジェンダー面や社会的価値観の変化を考慮し、複数の視点から事前モニターをしていたか疑わしい。特に「男性版のCM」との落差が大きいことも炎上原因の一つ。
- 無意識の刷り込み
- 男性社員が中心となった企画会議では「女性キャラが頬を赤らめるなんて普通に可愛いでしょ?」程度で通ってしまうかもしれない。そこに根付いた古いステレオタイプを見逃した可能性が高い。
3-2. “炎上マーケティング”ではなく、ブランドイメージの毀損
時折、「意図的に炎上させて注目を集めるマーケティング手法」が話題になりますが、今回のケースでは企業にそこまでの狙いはなかったように見えます。むしろ女性消費者からの批判やブランドロイヤルティの低下が懸念されるダメージです。
- 外資系コンサル的視点から言えば、企業の広告戦略は「短期的な話題づくり」ではなく「長期的なブランド価値向上」が重要。今回のような炎上は、むしろブランドイメージの負債になりかねません。
4. 男性版CMの落とし穴:男=仕事、女=家庭・感情?
4-1. 男性も女性も“暖まってホッとする”はずでは?
男性版CMでは、夜遅くまで残業する男性教師が「緑のたぬき」を食べる様子が淡々と描かれ、そこに涙や頬染めの要素はありません。
- 男性=皆が帰った学校で残業している
- 女性=家で感動して泣いている
こうした構図は無意識に「男性は仕事人間」「女性は感情的で家にいる」というステレオタイプを助長しないか?
逆に、男性が自宅でドラマを見ながら暖かいカップ麺でほっと息をつく表現でもよかったはずですし、女性が仕事終わりに一息つく描写でもよかったはず。
結果として、「女性は家で泣き、男性は職場で冷静」というコントラストが際立ち、視聴者が違和感を感じる要因の一つとなりました。
5. 『めしぬま』の例とダブルスタンダード:食×性のややこしさ
5-1. 男性が恍惚状態で食事すると“キモい”?
「めしぬま」という漫画では、男性が食事する際に恍惚の表情を浮かべる描写があり、以前インターネット上で「気持ち悪い」「奇形だ」などの激しい批判を受けました。実は“食事に性表現を載せるな”という強い反発もあるわけです。
つまり、「女性の泣き顔で頬染め」に限らず、男性が官能的な表情で食べる描写もまた攻撃されていた事例がある。
性別問わず、「食と色気を結びつける表現がキモい」という層が一定数いることは認識しておくべきでしょう。
現に古来より、食と性は多くの場面で結び付けられています。
- 1. フード・ポルノ(Food Porn)
「食事の視覚的な官能性」に関する研究。
視覚的に美しい食事の画像や動画が、性的な興奮を呼び起こすのと同じ脳の領域を刺激することが示唆されている(Spence, 2017)。
ソーシャルメディア(Instagram, TikTokなど)における「食べ物の見せ方」の研究。
2. 精神分析と食欲・性欲の関係
フロイトは「食欲(oral desire)」と「性欲(libido)」を密接に関連づけ、幼児期の口唇期(oral stage)における経験が性の発達に影響を与えるとした(Freud, 1905)。
食事の行為が「欲望」「満足感」と結びつきやすいことが指摘されている。
3. ガストロセクシュアリティ(Gastrosexuality)
料理をすることがセクシュアリティの一部になる現象。
「料理が上手な男性は魅力的に見える」という文化的な視点(Hollows, 2003)。
料理番組やレストラン文化において、セクシーなイメージが演出されることも指摘されている。
4. フード・フェティシズム(Food Fetishism)
食べ物とフェティシズムの関係。例えば、チョコレートや牡蠣が媚薬として扱われる文化的背景。
口に何かを入れる行為が性的なシンボリズムを持つ(Barthes, 1961)。
「食べる」行為が「支配・服従」のメタファーとして機能することもある(Bordo, 1993)。
5. 食事とジェンダー
女性が「控えめに食べること」を求められる文化的規範(Counihan, 1999)。
食事の量や選択が性的な魅力と結びつくこと(例:「サラダしか食べない女性 vs. 肉を豪快に食べる男性」のステレオタイプ)。
「女性の料理=家庭的」「男性の料理=プロフェッショナル」というジェンダー規範の分析。
6. 「食べること」とエロティシズム
食と性のメタファー:「舌」「口」「味わう」「飲み込む」といった言葉は性的な暗示を持つことが多い。
文学・映画における食のエロティシズム(『バベットの晩餐会』『シェフ』『ラ・グラン・ブーフ』など)。
儀式的な食事とエロス:例えば、バレンタインにチョコを贈る文化や、ウェディングケーキの儀式(新郎新婦が互いに食べさせ合う行為)。
5-2. それでも女性キャラへの攻撃が多い理由
他方で、「めしぬま」のように男性が性っぽい表現をしても批判されるケースがある一方、女性キャラが性的に描かれる表現は圧倒的に多く、なかなか改善されないという現状があります。
- 日本のアニメ・広告では、女性への性的視線(Male Gaze)が“デフォルト”になっている
- 男性が同様の表現をすると「気持ち悪い」と強く批判される傾向がある一方で、女性版は「見慣れているからOK」と見逃される場合もある
結果として「女性が食事するシーンに必要以上のフェチ要素が乗っていないか?」と注目が集まりやすくなるのです。
6. ビジネスリスクと炎上メカニズム:企業はどう対処すべきか
6-1. 炎上リスクは予測可能だった?
現代のSNS環境では、わずか1シーンの切り取りが一瞬で拡散され、深読み・誤読が加速して炎上することは珍しくありません。
企業が広告を制作するうえでジェンダーバイアスや文化的背景を精査するのは必須のフェーズでしょう。
- 多視点モニタリング:女性社員やジェンダー専門家によるレビュー
- 海外の受容度:もしグローバル展開する可能性があるなら、国ごとに感性が違うことも考慮
- 事前の危機管理プラン:炎上が起こった際の迅速な対応方針
これらを怠ると、企業の信頼資産を損ないかねません。
6-2. 対応が後手にならないための“ストーリーテリング”
広告やCMには、「なぜこの演出なのか」という物語(コンテキスト)を丁寧に伝えることで誤読を減らす手段もあります。
- 公式WebサイトやSNSで「女性版CM、男性版CMの演出意図」を詳しく解説
- 制作時の舞台裏やキャラクター設定を公表
- 声優を起用した場合は、キャラの魅力を一緒に語ってもらう
表面的な映像だけが拡散される状況を回避し、誤解を最小限にするのもマーケティング戦略の一部です。
7. 今回の炎上は何を映し出すのか:社会的意義と学び
7-1. 無意識のバイアスが映し出された“象徴的事例”
- 男性は職場、女性は家で感動して泣く → 性別役割分業の無意識が表出
- 頬染め・涙目=萌え表現 → アニメ文化の中で当たり前になっている女性の性客体化
これらのステレオタイプ的描写が、今回のCMに凝縮されてしまったからこそ炎上が起きたと見ることもできます。
7-2. 声優を目指す立場としての問いかけ
私自身、声優を志していた経験や声優として得た体験から、アニメやゲームで女性キャラがどう演じられるかに敏感です。
- 深く読みとると「従順さ」を要求されるキャラクターがあまりに多い
- “男に見下される女性”であることがオーディションで求められる
- 制作者側が「女性キャラならこういう表情や声がウケるよね」と決めつけている
上記のようなことに出くわすことが多く、夢のような世界ですが手放しで楽しい!と言えるものでもなかったのも事実です。
こうした問題は一人ひとりのクリエイターや声優だけでは変えられず、業界全体の意識改革が必要かもしれません。
8. 終わりに:炎上を“学びのきっかけ”に変えるマーケティングとは
今回の「赤いきつねと緑のたぬき」CM炎上は、日本人の古くからの無意識が反映されたとも言えますし、アニメ表現の女性の“性客体化”が批判を招いたとも言えるでしょう。いずれにせよ、企業マーケティングとジェンダー問題を考えるうえで貴重な事例となりました。
- 企業視点:ジェンダーリスクや文化的ステレオタイプを事前にクリアしておく重要性
- アニメ文化・声優視点:可愛さ演出があまりに偏ると、無意識の性客体化を助長しかねない
- 社会視点:男性は仕事、女性は感情的に泣くといったステレオタイプから脱却する必要性
企業が炎上を恐れて“無難”な表現ばかりに逃げ込むのではなく、多様な視点を踏まえて大胆なクリエイティブにも挑戦する。ただし、その際は「万が一の誤読」や「ジェンダーバイアス」をしっかり検証し、十分なコミュニケーション戦略を立てること。
炎上自体はネガティブな現象ですが、広告表現の問題点を社会が共有し、改めて自分たちの無意識を問い直すチャンスでもあります。
企業・クリエイター・消費者が対話を続けることで、より成熟したマーケティングとメディア表現を育んでいけるのではないでしょうか。
以上、元声優志望で現外資系コンサルタントの管理人Kotonoがお届けしました。